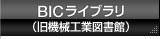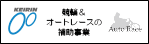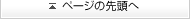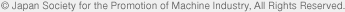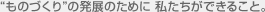研究会・イベントのご報告 詳細
「次世代型太陽電池及び定置用蓄電池の動向と課題」
| 主催:(一財)機械振興協会経済研究所主催 第487回機振協セミナー「次世代型太陽電池及び定置用蓄電池の動向と課題」開催報告 オンデマンド配信終了 | |
|---|---|
| 開催日時 | 2025年8月26日(火)14:00~16:00 |
| 場所 | WEBシステムにより開催(Zoom) |
| テーマ | 「次世代型太陽電池及び定置用蓄電池の動向と課題」 |
| 講師 | 公益財団法人未来工学研究所 政策調査分析センター社会課題調査分析センター 研究参与 多田 浩之 氏 シニア研究員 井上 敬介 氏 日鉄テクノロジー株式会社 サステナビリティソリューション事業部 産業・資源循環技術部 上席主幹 大内 邦彦 氏 |
| 内容 |
モデレーター: 機械振興協会 理事 兼 経済研究所 所長代理 北嶋 守 2025年8月26日(火)にWebシステムより、第487回機振協セミナー「次世代型太陽電池及び定置用蓄電池の動向と課題」を開催しました。講師は、公益財団法人未来工学研究所政策調査分析センター社会課題調査分析センター研究参与の多田浩之氏、シニア研究員の井上敬介氏、日鉄テクノロジー株式会社サステナビリティソリューション事業部産業・資源循環技術部上席主幹の大内邦彦氏にお願いしました。またモデレーターは機械振興協会理事兼経済研究所所長代理の北嶋守が務めました。当日は、122名にオンラインでご参加いただきました。ご参加いただきました皆様に、厚く御礼申し上げます。 【講演内容】本セミナーでは、次世代型太陽電池及び定置用蓄電池の動向と課題に関して、令和6年度に機械振興協会経済研究所が委託して実施された調査研究事業に基づき、2つの講演が行なわれた。講演1では、「次世代型太陽電池産業におけるサプライチェーンの構築と課題」について、公益財団法人未来工学研究所政策調査分析センター社会課題調査分析センター研究参与の多田浩之氏とシニア研究員の井上敬介氏が講演した。 先ず、調査研究の背景と目的を説明した。シリコン系太陽電池の技術開発では、以前は日本がリードしてきたが2005年以降中国などの海外勢に市場を奪われている。他方で、プロブスカイト太陽電池では日本が開発をリードしており、早期の社会実装と量産体制の確立が国際的優位性確保の鍵になっている。本調査研究は、プロブスカイト太陽電池のサプライチェーンの現状と課題を調査するとともに、サプライチェーン構築や市場への普及に向けた支援策について検討を行ったものである。 次に、日本におけるプロブスカイトの位置づけやその取り組みを紹介した。太陽光パネル市場は中国に独占されている現状を示すとともに、プロブスカイト太陽電池が軽量・柔軟ながらシリコンと同等の効率性を持ち、フィルム型・ガラス型・タンデム型と多様な形態で開発されている点から日本が現時点では開発をリードしているとの解説があった。一方で、実用化に向けた課題として、耐熱性・耐光性・耐湿性の克服が必要であり、量産技術に向けた成膜技術には日本で技術蓄積があるRoll to Roll方式が有望とされた。なお、特許面では日本が依然3割を保有するが、中国の台頭が顕著である。 こうした現状を踏まえ、本調査研究では、サプライチェーンの課題に関してヒアリング調査を行った。結果、原材料では、インジウムがフラットパネル・ディスプレイにも使用される素材であるため大量生産時に不足し課題となるとの声があった。また封止材、太陽電池の量産技術において、経済安全保障の観点からの技術流出懸念が指摘された。そして、応用製品としてはBIPV(建材一体型太陽光)が有力だが、耐久性・価格・建築基準法対応などが課題となっていた。さらに、設置可能面積の試算では、建物屋根や壁だけで政府目標の発電容量が十分確保可能と示された。 最後に、SWOT分析を用い支援策を検討した。日本はヨウ素資源や成膜技術に強みを持つ一方、インジウム依存が弱みであり、代替材料やバリアフィルム開発が重要とされた。支援策としては、①技術開発支援(代替材料・長寿命化・量産技術)、②情報流通の迅速化、③重要技術の輸出管理強化が提案された。また普及策として、ユーザー視点を踏まえた電力供給システムの構築、蓄電池を含む分散型電源システム構築、法規制整備、税制優遇、リサイクルシステム構築、地域エネルギーモデル形成といった提言が示された。 講演2では、「大規模再エネ機器導入に伴う定置用蓄電池の動向と課題」として、日鉄テクノロジー株式会社サステナビリティソリューション事業部産業・資源循環技術部上席主幹の大内邦彦氏が講演した。 先ず、蓄電システムの概要と市場概況を説明した。近年導入が進む再生可能エネルギーによる発電は天候や時間帯によって出力が変動するため、電気を一時的に蓄え必要な時に供給する仕組みが必要となる。その手段の1つとして系統用・再エネ併設の定置用蓄電池(以下、蓄電システムと呼ぶ)が注目を集めている。 蓄電システムは多層的な産業構造を持っている。素材メーカーが電池部材を供給し、セル、モジュール、ラック、コンテナと段階的に製品化される。これらを統合するのがシステムインテグレーターやEPC(Engineering、Procurement、Construction:設計、調達、施工を一貫して請け負う)事業者である。発電事業者はプロジェクトごとに最適な蓄電池メーカーを選定する傾向にある。自動車用蓄電池のように自動車メーカーと蓄電池メーカーが密接に連携するのとは異なる点で特徴がある。 主要な蓄電池としては、リチウムイオン電池、ナトリウム硫黄電池、レドックスフロー電池、ナトリウムイオン電池が挙げられる。リチウムイオン電池は短周期・長周期の両方に対応可能で、容量・出力性能にも優れ、普及の中心を担う。特に2013年から2023年にかけて価格が4分の1以下に下落したことは市場拡大を大きく後押しした。現在はリン酸鉄リチウム(LFP)が約7割を占めるが、今後は資源制約が少なくより安価にできるナトリウムイオン電池の採用が拡大するとみられ、目下中国企業の研究開発が進んでいる。 一方で、安全性は蓄電池産業の持続的発展に不可欠な課題である。世界で2011年から2024年までに88件の発火事故が確認されたが、特に韓国メーカー製が多く関与していたとされている。ただ、中国メーカーについては事故報告が極端に少なく、実際のリスクが十分に把握されていない可能性も指摘される。定置用蓄電池は遠隔モニタリングによる運用・保守が前提となるが、サイバー攻撃による制御障害など新たなリスクへの備えも不可欠である。安全基準の国際的整合性と実効性ある監視体制の整備が急務となっている。 市場規模に目を向けると、2023年の世界の系統用蓄電システム出力のうち中国と米国の二国で約8割を占めおり、日本はわずか1%にとどまっている。リチウムイオン電池の生産能力も8割が中国に集中し、韓国メーカーは積極的な海外拠点展開で市場対応を進めている。地域ごとの市場動向を見ると、日本は規模こそ小さいものの国内メーカーが過半を維持しているが、中韓製の浸透も進んでいる。米国や欧州はほぼ中韓製が中心であり、中国と韓国でも国内メーカーが独占的に供給し、自国市場での強固な地位を確立している。また政策面では、米国・ドイツ・中国・韓国は関税を課しているが、日本は課しておらず、蓄電池システム普及の産業政策も進んでいない。 こうした国際的な競争環境を踏まえると、日本産業界にはいくつかの対応が求められる。第一に、自助努力としてのコスト削減、生産能力拡大、システム統合を含む総合的競争力の強化、さらには遠隔監視・予兆診断など運用技術の高度化が重要である。第二に、産学官連携により、安全基準や技術開発に関する情報共有を促進し、国際ルール形成にも積極的に関与する必要がある。そして第三に、政府による産業育成支援が欠かせない。韓国のエナジーストレージシステム(ESS)に関する支援策は参考になる点が多く、日本もエネルギー安全保障や経済安全保障の観点から育成産業としての支援やモニタリング体制を強化することが期待される。 講演後は質疑応答が行われた。プロブスカイト電池の寿命やその普及に向けてのマイルストーン、各国で行われている自国企業優遇策の対象に現地生産を行う外国企業が含まれるかどうかに関する質問の他、リバースエンジニアリング等による技術流出への対策などについて議論がなされ、盛況裏に終了した。 動画の配信・資料の掲載は終了いたしました。 |